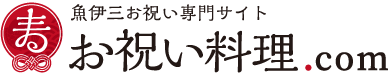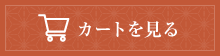「古希と喜寿のお祝いには紫色を」
前回、喜寿について記事にしました。その中で、古希の時と喜寿の時には紫色のちゃんちゃんこでお祝いするとお伝えしましたが、今回はなぜ紫色が重んじられるかについて書きたいと思います。
多くの方が紫色に高貴、上品といったイメージを持つのではないでしょうか。それをなんとなく当たり前に捉えていましたが、理由を調べると面白いものがありました。
現代では様々な染色技術がありますが、古代ギリシャの時代では、紫の染料は巻貝から作っていました。巻貝の吐き出す分泌液を元に作るのですが、一匹から採れる量は極めて少なく、1グラム作るのに数千匹の貝が必要だったため、高い身分の人しか使用できなかったそうです。
日本では、貝ではなく紫根という植物の根から染料を作っていましたが、やはりこれも簡単に作り出せるものではありませんでした。
聖徳太子が制定した「冠位十二階」という制度を聞いた覚えがありますでしょうか?日本初の階級制度(今時で言うとマウンティングでしょうか…?)が制定されたのですが、身分が一目で分かるように、12に分けられた階級によって冠の色を変えたのです。
そして、作り出すことが難しい紫色を最も高い位としました。
現代に続くカラーイメージが、実は聖徳太子の時代にまで遡るとは驚きですよね。東洋でも西洋でも同じように紫色を貴重な色と捉えるのも不思議なことです。
と、いうことで古希と喜寿祝いの本題とは外れましたが、お祝いする際の小噺の参考くらいになったら嬉しいです。
#古希と喜寿のお祝いにオススメ
大鯛焼き
特上寿司
舟盛り
NO.7会席
紫色のちゃんちゃんこ
大盃
練馬区、杉並区、西東京市、武蔵野市でお祝い事ならお祝い料理.comへ